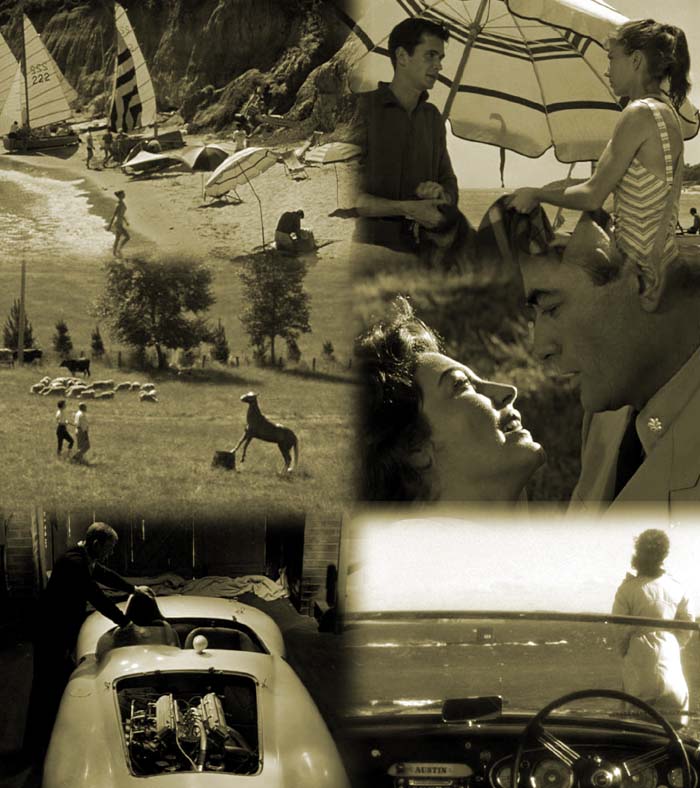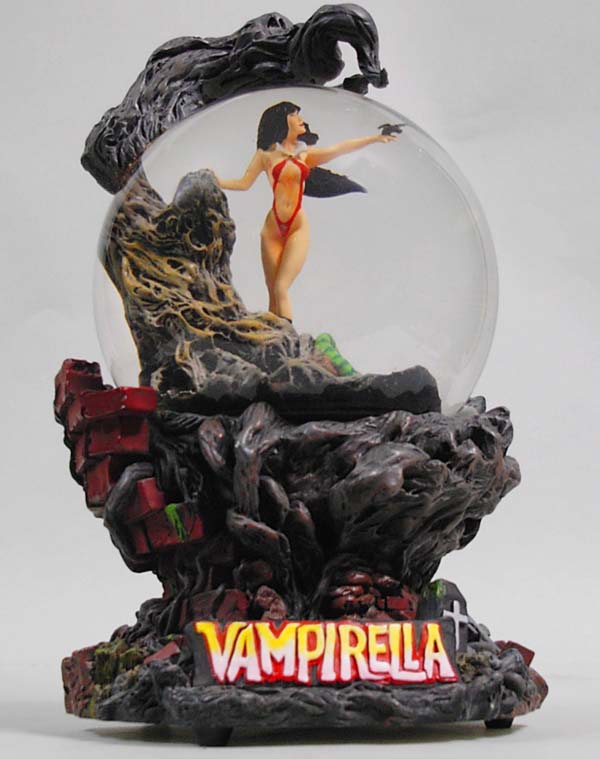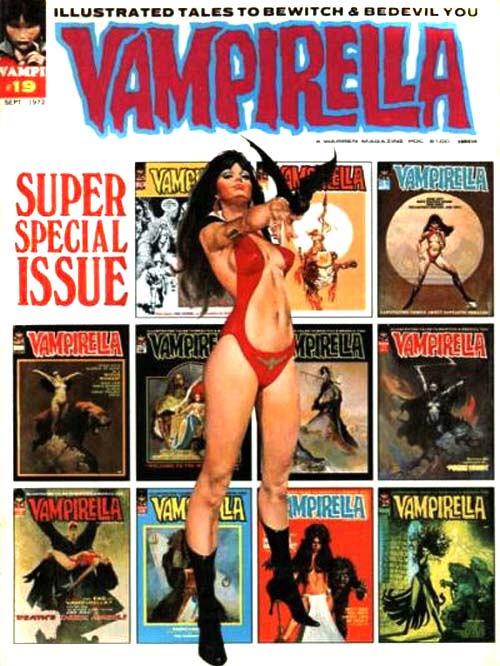1966年製作の『ミクロの決死圏』
物体を細菌大にまで縮小する技術が発明されたが、現時点での持続時間はわずか一時間。それを無限に持続させる方法を発明したチェコの博士が、アメリカに亡命する途上スパイに襲われた。脳内出血で昏睡状態にある彼の命を救うには、外からの手術では危険が多すぎた。そこで考え出された方法は、医師らを潜航艇ごとミクロ化し博士の体内に注入。博士の脳内出血部に到達させ、レーザー光線で治療するというものであった・・・
一時間という時間制限の中、潜航艇プロテウス号が患部を目指して人体内部を冒険するという奇抜なストーリーの作品です。
1970年代から80年代にはよくテレビで放映されていました。監督は『海底二万哩』(1954)のリチャード・フライシャー。
ところで、邦題の『ミクロの決死圏』というのは傑作ですね。
「決死圏」という単語、辞書にも載っていないのですけど・・・造語ですかね、これ?
この映画の最初の見どころは、時間をかけてじっくりと見せるプロテウス号と乗組員のミクロ化の過程でしょう。
人間がミクロ化するという荒唐無稽な設定でありながら、科学的な考証もしっかりとしているというなんとも不思議な映画ですが、実際に体内に入ってからは、次々と予期せぬトラブルに見舞われる事になります。
つまり、乗組員の中に敵国のスパイがいる、という設定ですね。一時間というタイム・リミットと、誰がスパイなのか、という二重のサスペンス。良く出来きた脚本だなぁ、という印象。
そして、この映画の最大の見どころは何と言っても人体内部の神秘的な映像でしょう。

人体ってこんなに明るくて綺麗なのか? 血液薄すぎないか? などという疑問は置いといて、ですね・・・科学的考証などと口にするのは野暮というもの。
原題は“Fantastic Voyage”
科学的な考証よりも、明らかに見せる事を重視した血管内の特撮は、現在見ても息を飲むほど美しく幻想的です。
よく、サルヴァドール・ダリが美術を担当したと紹介される事があり、私も長い事そう思っていましたが、これは明らかに間違いで、映画と同名の“Fantastic Voyage”というリトグラフ作品と混同され、映画の解説などで間違って紹介されてしまったとの事。
そういえば、ジェームズ・キャメロン製作、ローランド・エメリッヒ監督でリメイクの企画が進行中という話があったのですが、その後どうなったのでしょうか? 血液や液体をリアルに描いたらと思うとゾッとしますけど。
あとは・・・
紅一点、脳外科医の助手役のラクエル・ウェルチも作品に花を添えています。

ラクエル・ウェルチといえば、『恐竜100万年』(1966)が有名。この作品では結構知的な女性に見えますが、やはりお色気担当なのは明らかで、ぴっちりとしたウェットスーツ姿の彼女にまとわりついた抗体を、三人の男達が必死に抗体をむしり取るシーンがそれを象徴しております。
妙にエロチックで、しっかりと乳を触ってる奴もいるし・・・
最後は、誰もが疑問に思ったエンディング。
手術は成功したものの、制限時間ぎりぎりになって、プロテウス号を破棄しなければならない状況に陥ってしまいます。
人間だけは涙腺を伝って無事外へ脱出できたのですが、体内に残されたプロテウス号はどうなったのか? 一時間を超えると膨張が始まり、当然患者を殺してしまう事になります。
これは、アイザック・アシモフの小説を読めば解決されます。
ちなみにこの本は、映画の脚本を元にアイザック・アシモフが小説化した物で、原作ではありません。大きすぎる空気の分子、などの疑問も解消。映画を見た後に読んでも十分に面白いのでお勧めです。
しかし、小説を読んでも解消されない疑問が・・・
プロテウス号は、動脈注射で体内に入り、心臓、毛細血管、リンパ管、耳などを通って患部に到着するのですが・・・何故、そんな遠回りを? 患部の近くに注射すればいいのに、って子供の頃から不思議に思っていました。
これって何か理由があるのでしょうか?
もしかして、患部の近くに注射したら見せ場が全く無く、映画として成り立たないとか、そんな理由だったりして・・・